 |
| われわれの「社会」の学問、社会学は、身近にも感じるが、実は広くて深いもの。効率よくまとまったゼミネット公務員講座の社会学を、ちょっと読み込んでみるWEB版特別講義です。第5回は「大都会シカゴのひずみから社会を探れ!」! |
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 |
| 第5回 大都会シカゴのひずみから社会を探れ! |
|
1 シカゴ学派 シカゴ学派の成立には1920〜30年代のシカゴの状況が関係している。当時のシカゴはアメリカ第2の大都会であり、移民、人種差別、家族解体、非行など都市問題が山積していた。シカゴ学派の社会学はこのような現実の問題に向き合う中で発展した。中でもトマスの移民研究、パーク、バージェス、ワースらの都市社会学、ブルーマーのシンボリック相互作用論などが有名である。 |
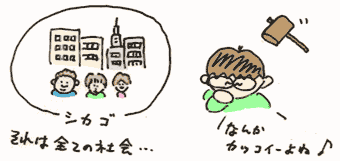 |
|
2 トマス トマスとズナニエツキの共著『欧米におけるポーランド農民』は、手紙や日記などの資料の利用、個人の生い立ちを詳しく記録した生活史(ライフヒストリー)など社会学の研究方法への貢献が高く評価されている。 |
|
【ここがポイント!】 <状況の定義付け> 例えば、デートの待ち合わせをしていて相手がなかなか現れないという経験があるだろう。そんなとき、自分が置かれた状況には色々な可能性がある。交通渋滞か何かでたまたま遅れているのかもしれないし、忘れているのかもしれない。最悪の場合、だまされたとかふられた可能性もある。そして、わたしたちが次にとるべき行動は、その状況の定義付けによって決まる。このように、人々の行為は客観的な状況に応じてなされるのではなく、主観的な解釈に基づ基づいて行われるのである。人によって経験や人格(パーソナリティ)は異なるので、当然状況の定義は異なり、誤解や衝突のもとになる。個人の状況の定義と、社会が個人に強制する状況の定義がくいちがえば、不適応や社会解体のもとになるとトマスは考えた。 <四つの願望> トマスは初め、社会現象を本能によって説明しようとしていたが、後には本能に代わって、欲求を人間行動の基礎と考えた。そこで出されたのが四つの願望説である。四つの願望とは・新しい経験の欲求:好奇心や冒険心を満たすこと。流行もこれに基づく。・安定/安全の欲求:危険や死を避けるために集団との結合を求める。変化を避ける点で・と対立する。・応答の欲求:恋愛や家族愛など個人的で親密な関係で認められることを求める。・認知/承認の欲求:名声や地位など世間から認められることを求める。人々はこれらの願望を妨げるものに対して、怒り、恐れ、憎しみを抱く。 |
3 パーク 人間生態学:生態学とは、動物や植物がある環境の中で互いにどのような関係を結びながら生活しているかを研究するものである。パークは都市をこのような相互作用の面から捉えようとした。それが人間生態学である。 |
|
【ここがポイント!】 ★パークによれば、都市とは単なる人間の集まりでも建物や道路でもなく、人間の心の状態であり、コミュニティとソサエティという2つの側面をもっている。コミュニティとは、動植物が生存競争をして、その結果分業や棲み分けがなされるのと同じように、人間が土地や資源をめぐって競争した結果できる地域社会である。このような経済的な競争の後、政治的な闘争を経て形成された社会状況に対して、人々は心理的な面で適応する。こうしてできるのがソサエティである。ソサエティは人々の共通の目的に基づいて慣習や伝統を保持している文化社会といえる。 ★人間生態学による都市理論としてはバージェスの同心円地帯理論などがある。 |
| ゼミネット公務員講座で、わかりやすく解説しています。 |
| 次回は 「真打登場!機能主義だぜ、パーソンズ」です。ご期待ください。 |
Copyright (C)2009 SEMINET, KNoT All rights reserved. |
||